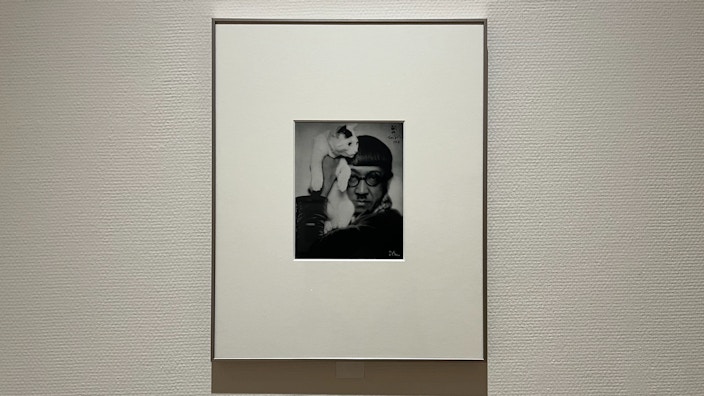原宿の地でリニューアルしたCCBT。SIDE COREが語るアーティストと都市をつなぐ場のあり方
アートとデジタルテクノロジーによる創造拠点「シビック・クリエイティブ・ベース東京(CCBT)」が、渋谷から原宿へと拠点を移す。新しいスペースでこけら落とし個展をおこなうのは、CCBTが展開してきたコア・プログラム「アート・インキュベーション・プログラム」の2022年度アーティスト・フェローであるSIDE COREだ。メンバーである松下徹、高須咲恵、西広太志、播本和宜が個展の内容とCCBTとのつながり、今後への期待までを語ってくれた。