書評:無感動から始まる美学への新しい道。ベンス・ナナイ『美学入門』
雑誌『美術手帖』の「BOOK」コーナーでは、新着のアート本を紹介。2025年7月号では、ベンス・ナナイによる『美学入門』を取り上げる。分析美学を専門とする研究者・ナナイによる、「感動できない」ことから美学を語り始める新しい美的感覚への実践的な手引書を、美術史学研究の青木識至が評する。
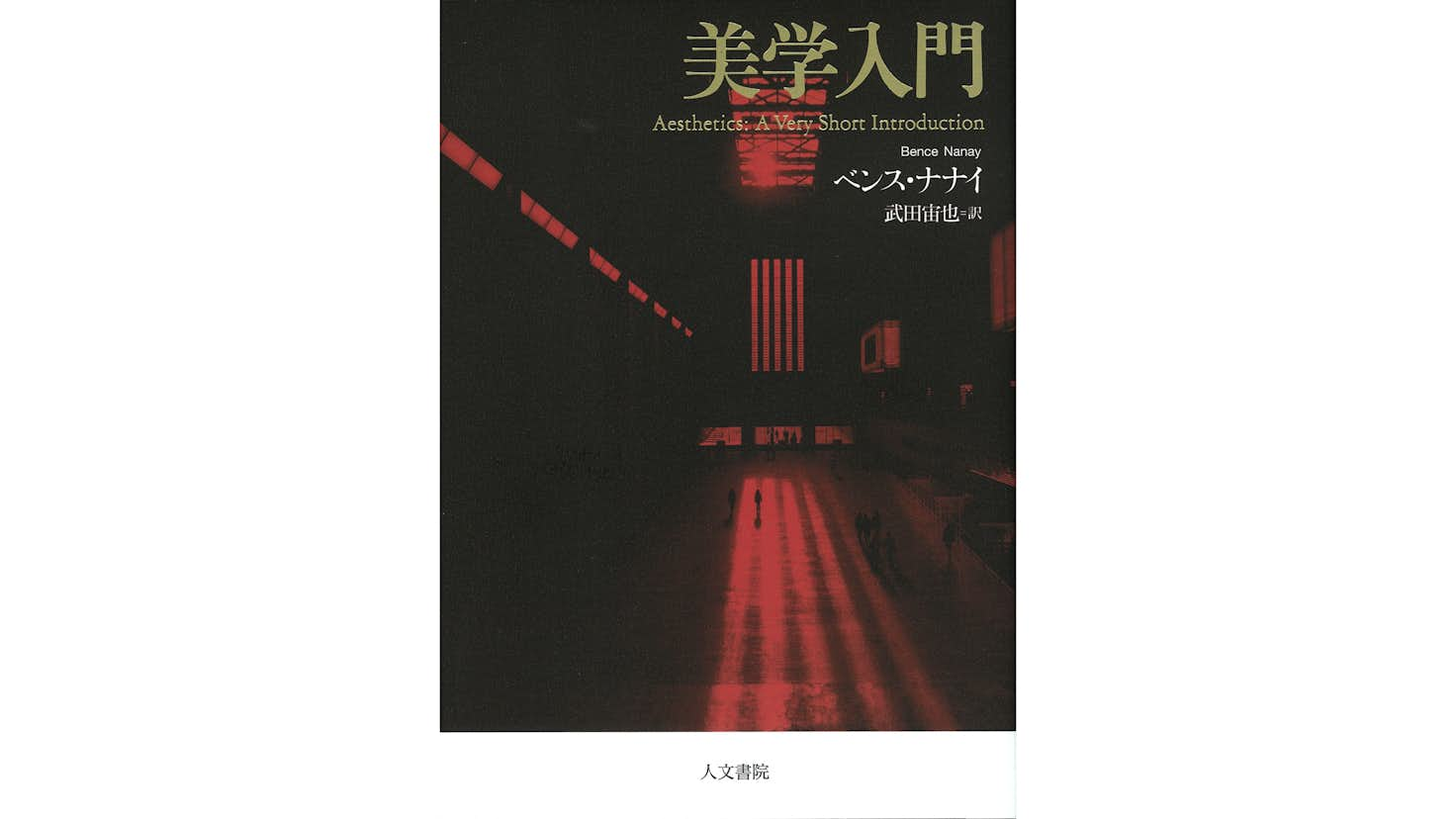
無感動から始まる美学への新しい道
美学という言葉には、なぜか「門」が多い。とにかく入り口はにぎやかだ。だが一歩なかに足を踏み入れようとすると、たちまち言葉の壁が立ちふさがる。美しいものに心を動かされたあの瞬間を、もっと理解したくて手に取った入門書。しかし、そこに並ぶ抽象的で難解な専門用語に気圧され、そっとページを閉じてしまう。そんな経験を持つ読者も少なくないだろう。
本書は2019年にオックスフォード大学出版局の入門シリーズ「Very Short Introductions」の一冊として刊行された原著の全訳である。著者のベンス・ナナイは分析美学を専門とする研究者で、現在はアントワープ大学哲学的心理学センターの教授を務めている。特筆すべきは、本書が美学を、感動ではなく感動できなさから語り始める点だ。冒頭、著者は美的関与が万人に開かれた自明な経験ではなく、しばしば「苦難の道のり」になると述べる。美術館や映画館、あるいはレストランで私たちがしばしばふれる無感動への戸惑い。ナナイが示唆するのは、まさにそうした経験こそが、美的なものの感受へと立ち返るための入り口になることだ。本書はその意味で、理論書である以上に、日々の生活に潜む美的経験と向き合うための実践的な手引きでもある。
ナナイの「門」の特徴は、その徹底した明快さと議論の具体性にある。美学の議論は、具体的な芸術作品を通して語られることも多いが、その解釈の幅広さがかえって読者を惑わせることもある。対して本書は、具体的な作品を時に引用しながらも、あくまで日常的な経験に即したまま美学を解き明かしていく。訳者の武田宙也も指摘するように、とりわけ興味深いのは「注意」をめぐる議論である。私たちの注意のありようがどのような美的差異を生むのか。注意が拡散する現代において、こうした問いにこそ本書は答えている。また、本書が美学に関わる文化的背景の違いにも目を向けている点は見逃せない。後半の一章はその考察にあてられている。
平易な文体で書かれ、予備知識なしでも読めるという点で、本書は数ある「美学入門書」のなかでも、もっとも敷居の低い一冊だろう。ただし、西洋美学の理論的伝統を概観したいと手に取った読者には、肩透かしに映るかもしれない。もちろん、本書がそうした議論と無縁なわけではない。だが本書の本領は、そうした歴史的総覧ではなく、現代の読者が直面する美的経験の問題と、美学をいかに接続し直せるかにある。巻末には本文の注釈を担う参考文献に加え、整理された読書案内もある。こうした構成にも、実践的な読者へのまなざしが感じられる。
(『美術手帖』2025年7月号、「BOOK」より)