書評:家庭から見た戦時の画家の姿。松本莞『父、松本竣介』
雑誌『美術手帖』の「BOOK」コーナーでは、新着のアート本を紹介。2025年7月号では、松本莞による『父、松本竣介』を取り上げる。日本近代洋画家として知られる松本竣介の、画家の枠を超えたゼネラリストともいえる姿を、生活者としての側面から竣介の次男・莞が記した本書を、美術批評・中島水緒が評する。
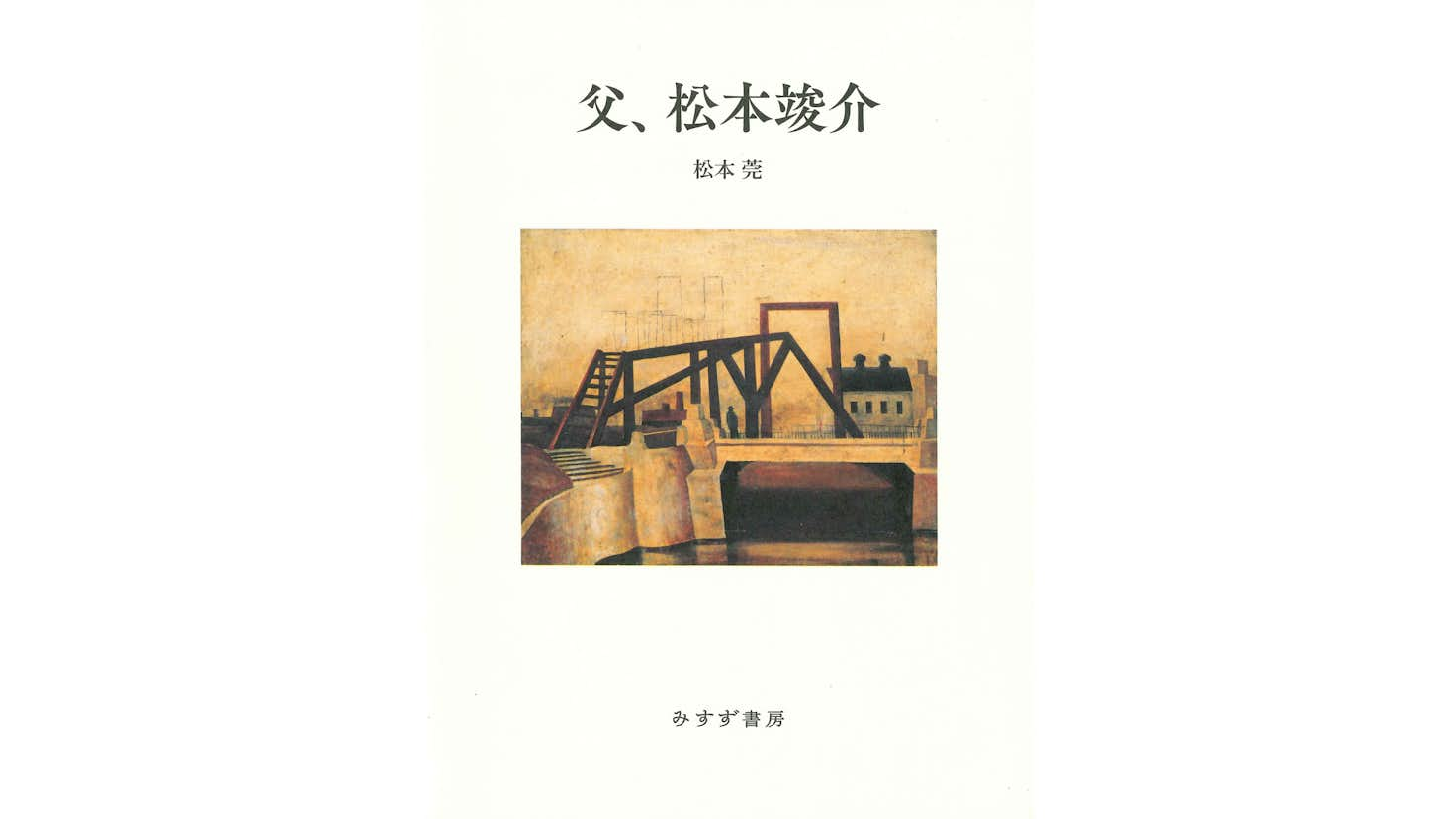
家庭から見た戦時の画家の姿
評伝の醍醐味のひとつは、対象人物のパブリック・イメージがいかに解体されるかにある。家族や友人など近親者による証言、学術目的の研究書や批評文の類では記述されない人物像、エポックメイキングな仕事の陰に隠れた知られざる活動。そこに定説を覆す新事実などが加われば、なおのこと面白い。
松本竣介といえば、近代的自我の記念碑とも言うべき《立てる像》(1942)をはじめ、心象を投影した抒情的な東京風景などが一般によく知られている。少年時代に病気で聴力を完全に失った経緯もあり、どこか孤高のイメージがつきまとう画家だ。その道程を出生のルーツから死後の評価まで整理すべく、竣介の次男・莞が本書を著した。家族という親密な関係ならではの述懐を期待するも、その筆致からは一定の距離感が感じられる。ナイーヴな作風同様、竣介の内面がどことなくヴェールに包まれたままなのだ。竣介が36歳の若さで早逝したこと、戦中の疎開で父子離ればなれに過ごしたことなども距離感の理由だろうが、たとえ家族の前であれ、竣介自身が赤裸々な内面吐露を控える人物だったのかもしれない。
とはいえ、様々な関係者の証言や遺品・資料精査を経た著者の記述は、「家庭」というプライベートな領域からの視点を十分に含んでおり、竣介の画家としての仕事を何が下支えしていたかを明らかにするものだ。若き日は妻の禎子とともに身銭を切って総合文化誌『雑記帳』の刊行に励み、言論の活性化を目指した。戦中・戦後は科学映画の動画描きのほか、雑誌の装幀・挿絵を手がける職人仕事で生活の苦境を乗り切った。著者は、竣介は絵だけのスペシャリストではなく画家の枠を超えたゼネラリストであったと主張する竣介の小学校時代の恩師の見解に同意しているが、この視点は竣介の多才ぶりが個人主義の芸術表現だけでなく共同作業でも発揮されたことを知るうえで非常に重要である。
純粋培養されたかのような竣介の絵画世界のバックヤードには、家庭を守り、小さな共同体の大黒柱として戦中・戦後の動乱期を乗り越えようとする静かな格闘があった。生活者としての竣介を知ると、画家が繰り返し描いた家族像や、1941年に竣介が『みづゑ』誌で発表した「生きてゐる画家」といったテキストへの理解もさらに深まってくるはずである。
(『美術手帖』2025年7月号、「BOOK」より)