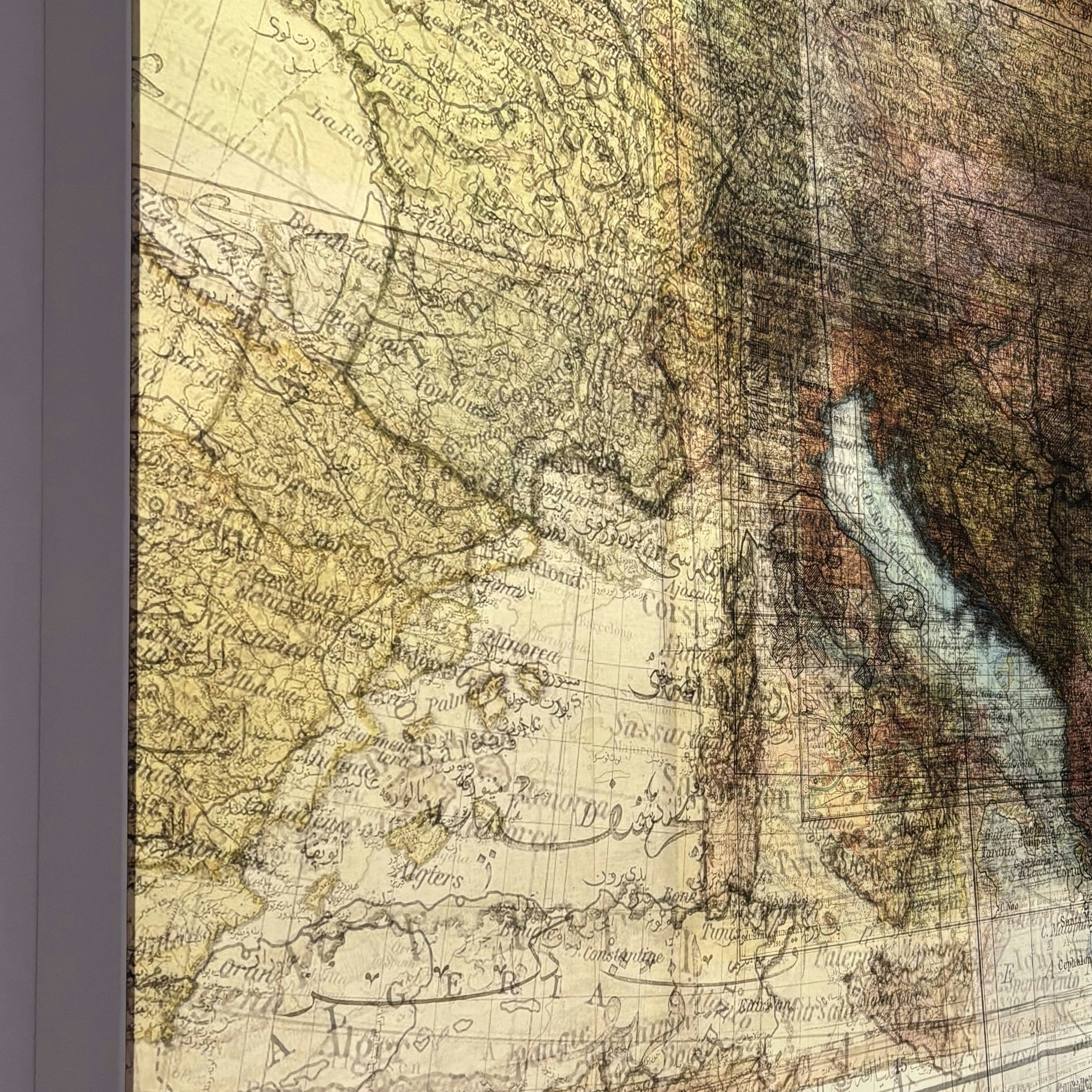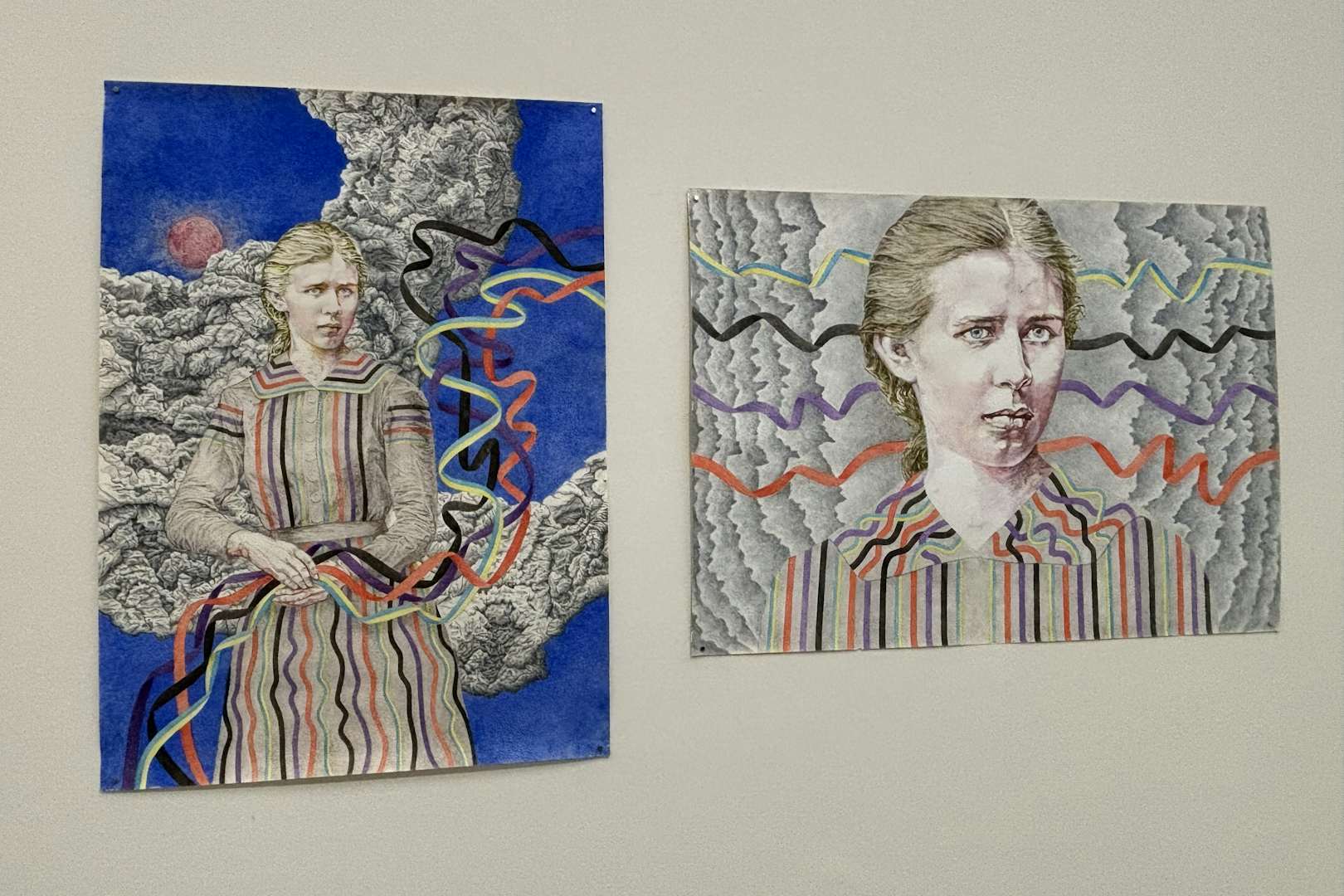未完の革命の継続としての連帯──ヨーロッパを周縁から問い直す「キーウ・ビエンナーレ2025」
2015年から開催されており、今回で6回目の開催を迎えたKyiv Biennial(キーウ・ビエンナーレ)。ロシアによる侵攻下で2回目の開催となった今年の「キーウ・ビエンナーレ2025」を、現地からキュレーター・慶野結香がレポートする。

Kyiv Biennial(キーウ・ビエンナーレ)は、2015年から開催されており、今回で6回目の開催を迎えた。主催はキーウに拠点を置く視覚文化研究センター(Visual Culture Research Center)。2021-22年のロシア・ウクライナ危機後、ロシアによるウクライナへの全面侵攻下においての開催は2回目となった。しかしマイダン革命、2014年クリミア危機以降から続くウクライナ紛争の長期化を考えれば、このビエンナーレは危機とともに始まり、継続されていると言える。
2015年、第1回目のタイトルは「The School of Kyiv(キーウの学校)」であったが、ウクライナおよび国際的なアーティスト、知識人、そして一般市民の対話を促す、6つの「学校」という概念的プラットフォームが設けられていた。そして翌年春にはその学校がヨーロッパ各地に拡張され、複数の都市に「分校」が開設されたのだった。ビエンナーレを「アート、知識、そして政治を結びつける国際的なフォーラム(*1)」として位置づける姿勢は、ウクライナへの渡航が難しくなった現在においても、だからこそ健在だ。

2023年版に引き続き、今回の「キーウ・ビエンナーレ2025」もヨーロッパ各地、複数の会場で開催されている。今回はヨーロッパの美術館、アート機関、大学による連合体 L’Internationale(ラ・アンテルナシオナル)との共催で、2024年に開館したポーランド・ワルシャワのMuseum of Modern Art(現代美術館)をメイン会場(2025年10月3日〜2026年1月8日)とし、展覧会はベルギー・アントワープのM HKA(アントワープ現代美術館、2025年10月9日〜2026年1月11日)、ウクライナ・ドニプロのDCCC(ドニプロ現代文化センター、2025年10月23日〜2026年2月7日)、キーウのDovzhenko Centre(国立オレクサンドル・ドヴジェンコ映画センター、2025年10月24日〜12月28日)、オーストリア・メンフィスのKunstraum MEMPHIS(クンストラウム・メンフィス、2025年11月11日〜12月5日)、同じくリンツのLentos Kunstmuseum Linz(レントス美術館、2025年11月11日〜2026年1月6日)の4国6会場で、異なるテーマを掲げて開催される。そのほか、M HKAでの3日間にわたるフォーラム、DCCCでのトークやスクリーニング・イベントも含まれるが、本稿ではワルシャワのメイン会場の様子を中心に、サテライト会場の一つであるアントワープ現代美術館での展覧会にも触れたい。
*1──「キーウ・ビエンナーレ」Webサイトより