書評:萩原弘子『展覧会の政治学と「ブラック・アート」言説──1980年代英国「ブラック・アート」運動の研究』
1980年代に「ブラック・アート」研究を始め、その領域では第一人者とも言える萩原弘子が2022年に刊行した書籍『展覧会の政治学と「ブラック・アート」言説──1980年代英国「ブラック・アート」運動の研究』の重要性を、文化研究者・山本浩貴が読み解く。
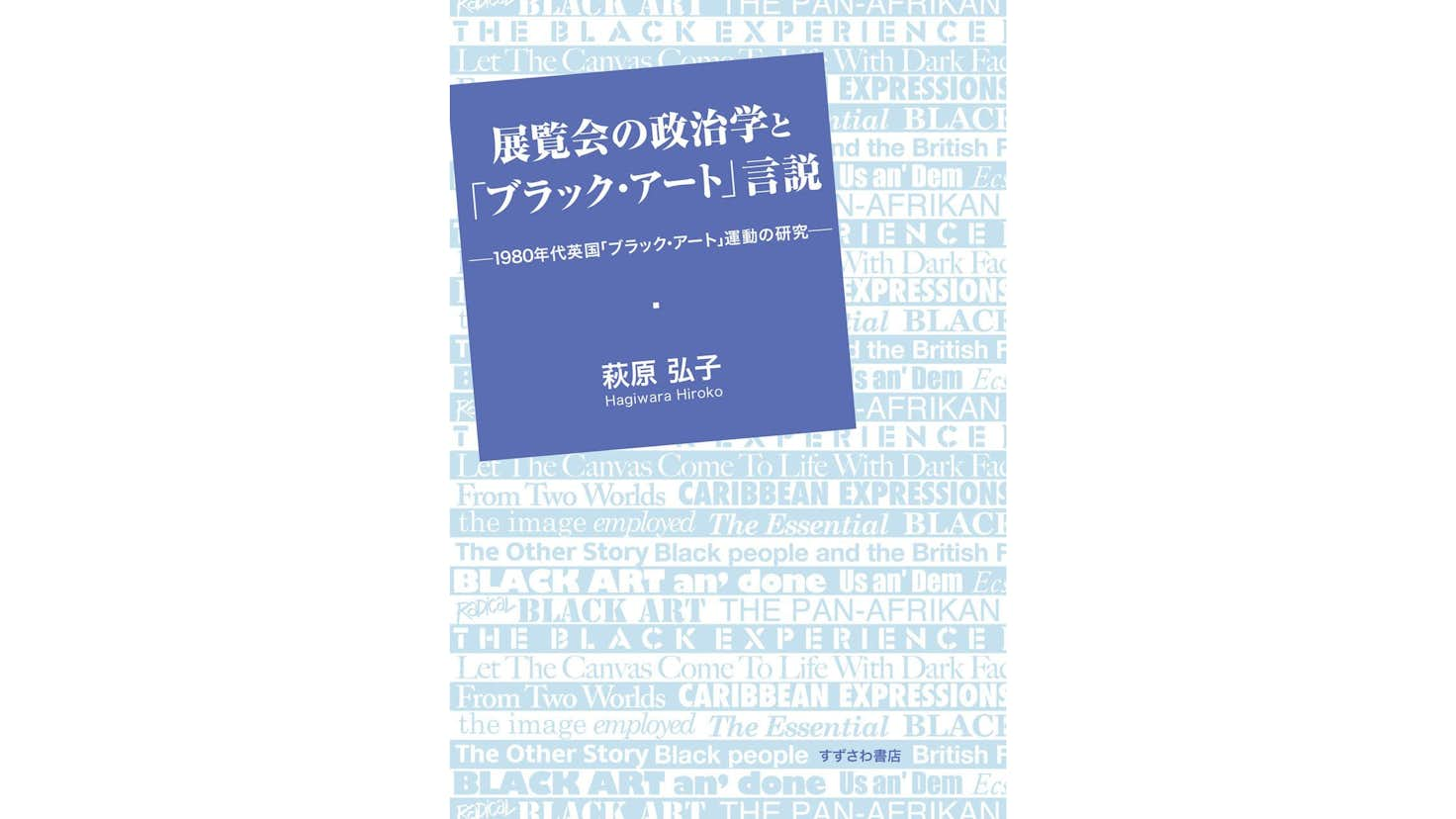
以前に私が『美術手帖』で「ブラック・アート」特集の監修を任されたとき、萩原弘子に協力を依頼したことがある。結果的に、誌面では小笠原博毅との素晴らしい対談が掲載された。その際に萩原から、ちょっとした「苦言」を頂戴した。
依頼に際し、私は「(とくにイギリスにおける)『ブラック・アート』研究のパイオニア」として力を貸してもらいたいと萩原に伝えた。一字一句、正確に覚えてはいない。だが、そのときに彼女から「自分は現役の研究者で、まだ『パイオニア』扱いは困る」という趣旨の返答をもらった。
萩原は1980年代に「ブラック・アート」研究を始め、この領域の道なき道をほぼ独力で切り開いてきた「パイオニア」だ。そのことへの感謝と敬意を含め、その見方は私の中で今も変わらない。だが『展覧会の政治学と「ブラック・アート」言説──1980年代英国「ブラック・アート」運動の研究』(すずさわ書店、2022年)は萩原の「現役の研究者」という矜持を、これ以上ないほどに体現した著作だと私は感じた。
なぜなら管見の限り、同書は日本のみならずグローバルな視野の中でも「ブラック・アート」研究の最先端にある。かつ、それに類する研究における現時点での到達点を示すと私は理解している。
この短評では、その全体像に言及することはできない。そこで個別に論じたい点は多いが、ここでは最近の私自身の仕事に引きつけて論を展開する。その中で、なぜ『展覧会の政治学と「ブラック・アート」言説』が当該の領域における「現時点での到達点」だと私が考えるかを説明したい。
字数が限定されているので、結論から述べる。萩原は、1980年代のイギリスにおける「ブラック・アート」運動と関連する展覧会を詳細に分析している。そうすることで、本書は同運動をめぐる「オペレーション」と「エンゲージメント」の総体を描き出すことに成功している。その総体の中には、その運動の周囲に張り巡らされた言説が含まれる。
長らくアメリカを拠点に活動してきた美術史家の富井玲子の初の日本語の単著『オペレーションの思想──戦後日本美術史における見えない手』(イーストプレス、2024年)が近年、刊行された。同書で富井は、「オペレーション」を「〈表現〉を社会化するさまざまな回路の総体」と定義する。その概念を構成する要素は、「美術館や画廊、美術学校のような制度だったり、批評家や画商、学芸員などの第三者たち」を含む。
対して、「エンゲージメント」はジャスティン・ジェスティ『戦後初期日本のアートとエンゲージメント』(コーネル大学出版局、2018年)の核となる概念だ。同書でジェスティは「リーフレットを配布すること、勉強会に出席すること、授業を組織すること、教えること、集会に行くこと、芸術作品を運ぶこと、手刷りすること、ものを郵送すること、交渉すること、予期せぬ主題について調べること、展覧会の設営・撤去を行うこと、インタビューすること」など無数の極めて日常的な営みの重要性を強調し、芸術を通じた社会的前進や政治的変革の基盤となる共同・協働的で組織的作業の総体を描く。
「隙あらば宣伝」の精神を発揮して恐縮だが、『戦後初期日本のアートとエンゲージメント』は私の単訳で水声社から近刊(2025年8月末)予定だ。7年前に出版された同書を翻訳するにあたり、著者であるジェスティから現在の視点を加えた日本語版への序文を書き下ろしてもらった。また、私自身も日本の文脈に引き寄せた1万5千字超の解説を寄せている。ぜひ、手に取ってもらいたい。
さて本書は、約15年間に開催された「ブラック・アート」関連の100を超える展覧会を仔細に分析する。参加作家や会場・会期などの情報はもちろん、付随するパンフレットや助成にまつわる政策文書までもその広範な対象となっている。これらの展覧会の主催者だけでなく、その助成者も主体的に文脈形成に関与したことが明らかになる。
本書は「ブラック・アート」を人種差別(レイシズム)という外的な社会背景だけではなく、その内部で作動する複雑な力学を捉えて多角的・複層的な解析を加えている。ともすると「ブラック・アート」研究では、しばしば記号的・象徴的な読解が先行しがちだ。だが萩原は実証的な証拠を積み重ねて、「ブラック・アート」言説をめぐる展覧会の政治学を解剖する。本書が、その到達点たる(と私が考える)理由がここにある。
その力学を萩原自身は本書で「政治学」と呼ぶが、上述の「オペレーション」(富井)や「エンゲージメント」(ジェスティ)の概念に近いと私は捉えた。ここには単に「ブラック・アート」の研究に留まらず、戦後・現代日本美術史との比較研究的な接続を図ることのできる可能性が生まれている。
本書が扱う1980年代以降、「多文化主義」が開花したことはよく知られる。同時に、その失敗した部分も現在では明らかだ。1980年代から90年代にかけ、エスニック・マイノリティをアートに包摂するための言説の構築が進められた。その構築は、「誰がその言説の主体か」という問いをめぐる抗争を伴った。『展覧会の政治学と「ブラック・アート」言説』では、これらの点が明らかにされた。
では1990年代以降の「失敗」において、それ以前との接続性をどこに見出すことができるのか。それは本書が提示する課題でもあり、私を含めた研究者が引き継ぐべき仕事だ。そのためには、「生涯現役」を貫く萩原の知見が私たちにはまだ不可欠である。
もうひとつ、論点を提示したい。それは、カルチュラル・スタディーズ(文化研究)と「ブラック・アート」の相互関係である。私は研究者として、自身が拠って立つ基盤をカルチュラル・スタディーズという学問分野だと考えている。(必要があるときは)自ら、「文化研究者」と名乗ってきた。
私はイギリスで批判的文化研究(critical cultural studies)の教育を受け、本書で萩原が詳細に検討するスチュアート・ホールやポール・ギルロイの著作から大いに学んだ。一般的な理解では、ホールやギルロイは「ブラック・アーティスト」に多大な影響を及ぼしたとされる。また、彼らは「ブラック・アート」言説の構築に非常に貢献した。
これらは、紛れもない事実だ。だが『展覧会の政治学と「ブラック・アート」言説』、とくに第IV部は強い説得力をもって認識の修正を迫る。同書は、むしろホールやギルロイがブラック・アーティストたちとの交わりの中で自身の理論を形成していった様を描く。カルチュラル・スタディーズと「ブラック・アート」の歴史的な発展過程は、明確に相補的な関係をなしている。
と、このように議論の種は尽きない。萩原弘子『展覧会の政治学と「ブラック・アート」言説──1980年代英国「ブラック・アート」運動の研究』は、私たちが深掘りすべき糧を豊富に含む土壌なのだ。
だが残念なことに、私の知る限りでは本書の書評はまだまだ少ない。オンライン・ジャーナル『ART iT』には、映像作家の藤井光が素晴らしい書評を寄せている。そこで藤井は、この著作が彼自身の「今後の創作活動にいかにして(…)作用するか」を論じている。
藤井が明らかにするように、本書は美術作家にとって優れた「実用書」である。だが同時に、(私がそのことを示せていることを願うが)研究者にとっては考察すべき課題を大量に含む「必読書」だ。
ゆえに、研究者による「黙殺」状態という現状は「残念」と言わざるを得ない。実践者にも研究者にも本書がさらに広く読まれ、その内容が建設的で批判的な議論に晒されることを切に望む。